 |
構造有機化学研究室とは...特異な分子構造を有する化合物には特異な電子構造が宿る。構造有機化学は自然界には存在しない新規な化合物を創出し、その化合物を通じて新たな物性や機能を追求する学問であると考えています。我々の研究室では独自の分子設計に基づく新規π電子系化合物を基盤として、中程度のπ結合性を有する分子の化学、大環状分子の化学、光・酸化還元応答性分子の化学、三次元拡張π電子系の化学、分子キラリティーの化学、金属錯体を用いた水素結合型電荷移動錯体の化学、など幅広く研究を展開しています。独創性豊かな分子を創り出す。そんな楽しみを味わえることが、構造有機化学研究室の最大の特徴です。 |
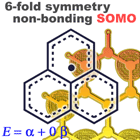 |
フェナレニルラジカルを基盤とする分子の単分子及び分子集合体の研究 フェナレニルラジカルは6回対称性の非結合性SOMOを有する開殻炭化水素分子である。不対電子の非局在性のため、熱力学的に安定化されたラジカル種である。電子の授受能に優れ、しかも分子間での軌道の重なりが大きいため、導電性物質の構成成分として優れていることが理論的に予測され、最近実験的にもそれが証明されつつある。我々はこのフェナレニルラジカルの特徴を生かして、1)中程度のπ結合性(一重項ビラジカル)の化学、2)炭化水素強磁性体、3)炭化水素ラジカル導電体などの研究を展開している。 |
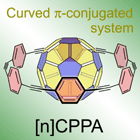 |
新規曲面π共役系分子の研究 カーボンナノチューブなどの新しい炭素同素体の多くは曲面状の共役系シートが積み重なった構造をしている。従って、曲がったシート間にはたらく相互作用はその生成や特性の発現に重要な役割を果たしていると考えられる。我々は、ナノメータースケールの円筒状の構造をもつ共役分子(カーボンナノチューブの輪切りのような構造から我々はカーボンナノリングと呼んでいる)を合成し、フラーレン類と非常に安定な錯体を生成することを見いだした。これは、曲面状の共役系間にかなり強い引力的な相互作用が働いていることを示している。現在は、種々の構造をもつカーボンナノリングを合成し、その超分子化学的性質を検討している。 |
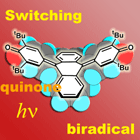 |
外部刺激応答性分子としての非平面性拡張キノノイド系分子の研究 分子が2つの異性体間を光や熱,電子授受などの外部刺激に応答して可逆的に変化すれば、その分子はスイッチング機能を持つと言える。我々はスイッチング分子の新たな基本構造を求め、ベンゾ縮環による非平面化を鍵とした様々な非平面性拡張キノノイド系分子を合成し、その外部刺激応答性を研究している。 |
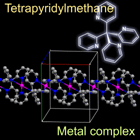 |
テトラキス(2-ピリジル)メタンの合成と金属錯体の構造に関する研究 テトラキス(2-ピリジル)メタンは対称性が高く美しい分子であるというだけでなく、ピリジン環の窒素原子が遷移金属に対して配位能を有することから遷移金属錯体の構造・機能に興味が持たれる。テトラキス(2-ピリジル)メタンの銀錯体は左図のような一次元の配位高分子を形成する。他にも種々の遷移金属と安定な錯体を形成することがわかった。テトラキス(2-ピリジル)メタンは遷移金属イオン、あるいはカウンターアニオンにより多様な配位パターンをとるので金属錯体の構造・機能の制御ができると期待される。 |
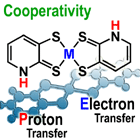 |
金属錯体を用いたプロトン-電子連動系の開発 水素結合を有する電荷移動錯体を基盤として、プロトンと電子が連動する系の構築を目指している。分子としては金属錯体を用い、プロトン移動と電子移動が容易に起こるような新規物質の創出を行っている。固体中でのプロトンの変位が分子間の電子移動にどのような影響を与えるか、ひいてはプロトン移動が導電性や磁性へどのような影響を与えるかが、興味のポイントである。 |