|
「身の回りを化学の目で見れば」 体験実験テーマと概要 |
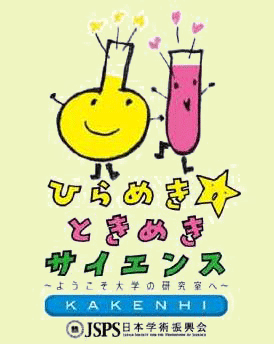 |
||||||
|
1.「試験管でできる炎色反応」 食塩の水溶液を金属の針につけて炎であぶると黄色く光ります。それが炎色反応で、見たことがある人も多いと思います。今回は同じ炎色反応でも試験管の中で 行う炎色反応の実験を行います。激烈な反応で、ちょっとアブナイので慎重に行います。その代わり、すごく強い光が発生します。混ぜる金属を変えると様々な 色の光が出ます。それは花火が光る原理と全く同じです。打ち上げ花火を遠くから眺める代わりに試験管の中で作ります。 2.「家でもできる化学実験」 化学実験といえば学校の実験室でやるものと考えがちですが、その気になって家の中を見渡すと洗剤や調味料には化学薬品として十分使えるものがあります。今回は一般家庭にあるもので簡単な実験をしてみましょう。内容は,1) 酸化・還元反応,2)炎色反応,3)錯イオン(錯体化学)と,少し難しそう な内容ですが,身近な物で実際に体験し化学への理解を深めましょう。 3.「水+高分子=?」 私たちの身の回りには、水と高分子がたくさんあります。私たちも水と高分子でできています。そんなありふれたものですが、少しの工夫でいろんなものに変身します。その七変化の様子
を体験してみましょう。水と高分子からどんな七変化が見られるでしょうか、、、
4.「細胞からDNAを抽出しよう!」 食塩の水溶液を金属の針につけて炎であぶると黄色く光ります。それが炎色反応で、見たことがある人も多いと思います。今回は同じ炎色反応でも試験管の最近、自然科学の内容、ヒトの体などを取り上げたテレビ番組も多く、その中でも「ヒトの性格って遺伝子によって決まるの?」「遺伝子組み換え作物って体に 悪いの?」といった遺伝子に関する話題が後を絶ちません。世間の多くは、遺伝子の本体であるDNAに対して、「目で見ることができない小さなもの」「難し いもの」というイメージを持っているようですが、 今回、誰でも手軽に入手可能な鳥レバー、白子、タマネギ、ブロッコリーなど様々な材料からDNAを抽出し、「DNAは簡単に抽出できる」「実際に自分の目 で見ることが可能である」ことを体験してもらいます。 5.「夜の顔は別の顔−紫外線で光る錯体」 「暗いお化け屋敷の中で突如浮かぶ「青白い」幽霊の姿。でも、明るい場所で見ると「白」装束のはずなのに、なぜ「青く」見えるのでしょう?これは、紫外線を当てることによって、白装束に付着している物質を「青く光らせている」からなのです。 6.「導電性プラスチック」 私たちの身の回りにあるプラスチックのほとんどは電気を通さない絶縁体です。しか
し、白川英樹博士らが発見した"導電性高分子"と呼ばれる物質は、電気が流れる不思
議なプラスチック材料で、現在ではいろいろな分野で使われるようになってきまし
た。この体験実験では、電解重合という方法により導電性高分子の一つであるポリチオフェンを合成し、その電気抵抗測定や色の変化を観察してもらいます。そしてどの
ようなしくみで電気が流れるのかを理解してもらいます。
7.「太陽電池でエコを体験しよう」 化石燃料を全く必要としない太陽電池は近頃すっかりエコの代名詞のになってきています。でもどうやって太陽光が電気になるのか気になりませんか?その仕組みについて理解しつつ、最近新しく出てきた色素増感太陽電池を実際に作ってみましょう。色素増感太陽電池では色素が発電の重要な役割を担っています。どんな色素を使えば、発電ができるのか?紅茶や花びらなどいろいろな色素を使って試してみましょう。そして電気製品を動かしてみましょう。 8.「赤外分光器を用いた肌の潤い測定」 固体、液体、気体などほとんどの物質は赤外線を吸収します。しかし、吸収される赤外線の波長はその物質を構成する分子の構造によります。
9.「放射線を体験してみよう・身近な放射線」 “放射能”という言葉の皆さんのイメージはどんなものでしょうか? 10.「かおりのあるエステルの合成」 "におい"とは何でしょう? においの正体は空気中を漂う化学物質なのです。私たちは化学物質を"におい"として感じているわけです。花や果物にはさまざまな揮発性の化合物が含まれており、それらが混ざり合って特有の香りとなります。バナナやパイナップルなどの香りの主成分はエステルと呼ばれる物質であることが知られています。今回はカルボン酸とアルコールを用いていくつかの香りのあるエステルを合成してみます。何の匂いか当ててみましょう。
|
||||||
| ページTOPへ | |||||||