 天皇皇后両陛下の御臨席のもと開会式で主催者挨拶を行う金澤一郎日本学術会議会長.左は菅宏名誉組織委員長と阿竹徹組織委員長.
天皇皇后両陛下の御臨席のもと開会式で主催者挨拶を行う金澤一郎日本学術会議会長.左は菅宏名誉組織委員長と阿竹徹組織委員長.
つくば国際会議場において,2010年8月1日~6日に開催された表記国際会議に組織委員として,とりわけプログラム委員長として携わったのでここに記録を残しておきたい.主催は日本熱測定学会,日本化学会,日本学術会議であった.開会式とウェルカムレセプションには天皇皇后両陛下のご臨席を賜った.参加者は36ヵ国/1地域から665名(国外233名,国内432名)であった.本会議の名誉組織委員長は大阪大学の関集三名誉教授と菅宏名誉教授であり,組織委員長は東京工業大学の阿竹徹教授,事務局長は筑波大学の齋藤一弥教授であった.いずれも大阪大学の出身である.また,1996年に大阪で開催された国内最初の第14回(ICCT-96)では徂徠道夫名誉教授が実行委員長を務めており(本レポート,No. 17参照),いずれも誘致から実施まで大阪大学の熱グループ出身者が大きな役割をしてきた会議と言える.ちなみに本会議のウェルカムレセプションでは,菅先生が乾杯の音頭をとられ,光栄なことに徂徠先生と稲葉がそれぞれ,天皇陛下と皇后陛下の通訳を務めさせていただいた.
プログラム委員会は,組織委員会の助言の下に2年前から実際の活動を開始した.シンポジウムの企画・設定とそのチェア(基本的には日本側1名と外国側1名)の選任を行い,とりわけ全体講演者の選任を急いだ.最終的にはシンポジウム14件に加え,ワークショップ3件が企画された.このうち1件のワークショップ「Thermodynamics of Small Systems」は非常に興味深いテーマであったが,担当の両チェアが外国人でいずれも会議に参加できず,残念ながら直前になってキャンセルすることにした.また,シンポジウムの内1件は,関集三先生と菅宏先生のこれまでのご業績とこの分野での貢献を称える「Special Session in Honor of Prof. S. Seki and Prof. H. Suga」であった.以下にシンポジウムとワークショップの名称を記しておく.
<シンポジウム>
Fluids & Fluid Mixtures
Phase Equilibria
Foods & Pharmaceuticals
Biothermodynamics
Colloids & Interfaces
Thermochemistry & Molecular Energetics
Environmental Issues
Industrial Applications, Databases & Software
Theory & Simulation
Organic Materials & Polymers
Inorganic Materials & Metals
New Techniques
Education in Chemical Thermodynamics
Special Session in Honor of Prof. S. Seki and Prof. H. Suga
<ワークショップ>
Energy with Subsections on Petroleum, Coal and Alternative Sources
Calorimetry with Commercial Relaxation Instruments
アブストラクトの受付は,参加登録と同時に2009年12月末から始めた.ウェブサイトを通じて受付後ただちに審査を始め,3週間以内には受理通知を返信するという体制を取った.また,1人で複数の発表も歓迎した(実際,7件の発表を行った人もいた).参加者には,どのシンポジウムでの発表かについて第2希望までと,口頭かポスターかの希望を募った.実際には,よほどの事情がない限り発表者の希望通りに受理した.この審査には各シンポジウムの日本側チェアが当たった.それをプログラム委員長が統括するという作業の流れであったが,各チェアは多忙中にもかかわらず,締切までの数ヶ月間,この作業に携わって協力していただいた.
ところで,欧米で開催される国際会議と違って日本での開催となると,渡航費や滞在費がどうしても高額になりがちである.そこで,発展途上国からの参加を促すために「Travel Grant Program」と称する資金援助を行った.実際には参加登録料の無料化という意味合いであった.発展途上国の定義は難しいが,実際にはOECDの定義を参考に,これを少し拡大して認めることにした.その審査は,アブストラクトの審査と同時にプログラム委員会で行った.多数の申し込みがあったが最終的に35名について受理した.実際には内2名が参加しなかったが,その意義と効果は十分あったと思われる.
アブストラクトの締切は当初4月30日であった.しかし,直前に申し込みが集中したため,5月18日まで締切を延長した.ただし,プログラム作成の都合から,延長後の申し込みについてはポスター発表に限った.口頭発表のプログラム作成は,外国人チェアを含む全員で行った.全アブストラクトを読んだ上でのプログラム作成であった.この作業には大変な時間と労力を費やした.なお,プログラムの確定には,各発表者の参加登録料金の事前払い込みを条件とした.これは,会議当日になって不参加となりプログラムに穴が空くと折角の議論が中断するため,これを避ける措置であった.実際にはプログラム確定後も,病気などの理由で数件のキャンセルがあったが,最小限の変更でプログラムが極めてスムーズに実行できたのは幸いであった.1件だけ航空便のトラブルで当日での発表に間に合わず,後日の発表に回ったものがあったが,大規模な国際会議では不可避なのであろう.
発表は,ロッシーニ受賞講演(1件),全体講演(9件),一般講演は口頭(198件)とポスター(302件)の合計500件,これに各シンポジウム・ワークショップにおける招待講演(40件)があった.アカデミックプログラムは5日間に及んだが,大きな国際会議であるだけに7会場で平行してセッション(最終日は4セッション)を行わざるを得なかった.場合によっては,興味ある講演を聞き逃す場面があったかもしれない.しかし一方で,一般講演の口頭発表は20分間の枠を確保した.海外から参加して10分間の発表という国際会議もあるが,あまりに短いというこれまでの経験からであった.ポスター発表は3日間に分けて昼食後の90分間を充てた.
IACT(International Association of Chemical Thermodynamics)の企画としてJunior Award(30歳以下で優秀な発表を行う者に授与)を5名,事前に募った.提出されたアブストラクトと推薦状などを選考材料としたようだが,結果的にIACTは7名に賞を授与した.その決定時にはすでに全体のプログラムをほぼ確定しており,受賞者の中にはポスター発表を希望した者もいたが,プログラムを組み替えて,全員を口頭発表として各シンポジウムで発表できるように手配した.この措置は受賞者,IACT共に好評で喜んでいただいた.これとは別に,ポスター賞は3件に与えられた.論文集は,4種の雑誌〔Pure and Applied Chemistry,The Journal of Chemical Thermodynamics,Thermochimica Acta,Molecular Simulation〕の特別号として,各雑誌の通常の審査を経て2011年中に出版される予定である.なお,ポストコンファレンスとして本会議が終了後,大阪でThe 2nd International Symposium on Structural Thermodynamics (ISST-2010) を開催した(本レポートの別記事参照).
時系列としては逆転するが,ICCT-2010開催の前日(7月31日)に同じ会場で公開講演会が催された.この種の講演会は一般市民を対象とした啓蒙活動として重要で,最近の国際会議ではよく企画されるものである.今回のICCTではとりわけ,環境問題と化学熱力学の接点を探る視点を含んでおり,この講演会は重要な位置づけであった.近隣の中学生からICCTの出席者まで多数の聴講者があり,司会は稲葉が行った.
最初の講演は,カナダのダルハウジー大学のMary Anne White教授による「Energy and Temperature in Our Lives: The Role of Thermodynamics」であった.英語の講演でスライドも英語であったため,日本語に翻訳したスライドを事前に用意した.当日は2枚のスクリーンを使った逐次訳(および説明)を稲葉が行った.そのために,White教授にはカナダで近所の子供たちを集めてリハーサルを行い,そのスライドと音声を事前に送るなど周到な準備をしていただいた.聴講者の半数以上が日本人であり,このスライドと翻訳および説明は非常に好評であった.講演では,温度と熱の違い,ものの状態変化,太陽光発電から節電まで身近なエネルギー問題に言及された.
もう一つの講演は,組織委員長である阿竹徹教授による「地球環境と熱力学 —地球の熱収支と水—」であった.幼少の頃の体験と,熱力学の重要性,最も身近な物質としての水の不思議な挙動を含め,地球規模での熱力学研究の重要性が講演された.それぞれの講演後には多数の質問が英語・日本語で飛び交い,質疑応答など活発な議論が続いた.講演後もICCTの会議中に,参加者の間でいろいろな議論が個別に行われていた.
オックスフォード大学のPeter Atkins教授(今回のICCTの全体講演者の一人)は,多数の教科書(とりわけ物理化学)を執筆しており世界的に有名であるが,White教授の極めて教育的な講演を賞賛した上で,一つだけ修正したい点があると指摘した.それは,エネルギーの定義に関するものであった.White教授は「エネルギーとは,ものが仕事を成し得る能力」と定義したが,Atkins教授は単に「エネルギーとは,仕事を成し得る能力」とすべきだという主張であった.確かに,電磁場では「もの」は存在せず,それでいて「仕事を成し得る能力」は存在している.これは一例にすぎないが,この種の熱力学教育に深く関わる専門的な議論は,今回のICCTのシンポジウム「Education in Chemical Thermodynamics」でも活発に行われた.一般市民だけでなく専門家にとっても,いろいろな観点から今回の公開講演会は非常に意義深いものであった.
 天皇皇后両陛下の御臨席のもと開会式で主催者挨拶を行う金澤一郎日本学術会議会長.左は菅宏名誉組織委員長と阿竹徹組織委員長.
天皇皇后両陛下の御臨席のもと開会式で主催者挨拶を行う金澤一郎日本学術会議会長.左は菅宏名誉組織委員長と阿竹徹組織委員長.
 ウェルカムレセプションで参加者と歓談される天皇皇后両陛下.
ウェルカムレセプションで参加者と歓談される天皇皇后両陛下.
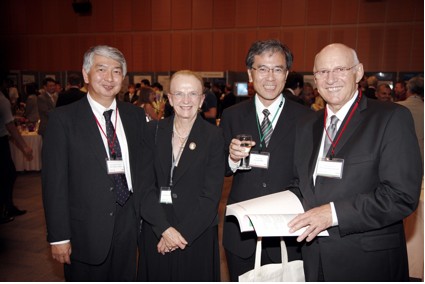 ウェルカムレセプションにて,国際諮問委員のJ.-P. Grolier教授(右端)夫妻と吉田博久日本熱測定学会会長(左端).
ウェルカムレセプションにて,国際諮問委員のJ.-P. Grolier教授(右端)夫妻と吉田博久日本熱測定学会会長(左端).
 公開講演会終了後のMary Anne White教授(左)と阿竹徹教授(中央).
公開講演会終了後のMary Anne White教授(左)と阿竹徹教授(中央).