
Emeritus Professor Syûzô SEKI
IUPAC化学熱力学国際会議が我が国で2度目に開催されるのを機に,構造熱力学という研究分野を確立され,熱測定討論会や日本熱測定学会の発足に先導的役割を果された関 集三先生(阪大名誉教授・日本学士院会員・日本学士院賞受賞),ならびにガラス状態とその緩和に関し卓越した研究をされた菅 宏先生(阪大名誉教授・日本学士院賞受賞)の業績を称える記念シンポジウムを開催したいとの要望が,阿竹 徹国際会議組織委員長(東工大教授)から国際化学熱力学連合 (IACT) に出され,快諾が得られた.それを受けて,門下生の小國正晴(東工大教授),松尾隆祐(阪大名誉教授),徂徠道夫(阪大名誉教授)とJuliana Boerio-Goatesさん(ブリガムヤング大教授)がシンポジウムのお世話をすることになった.企画は大きな反響を呼び,多数の発表申し込みがあった.まる2日間のセッションで招待講演5件,口頭発表13件,ポスター9件の発表を行った.
発表内容は,両先生の研究と関連して,水と氷の物性,ガラス状態と緩和,相転移が主であった.水と氷の物性は水素結合ネットワーク形成の多様性によってきわめて広い研究分野となっている.招待講演では,水の分子再配置緩和時間が0 °C近傍で非アレニウス的な挙動を示す一方,ガラス転移温度近傍でアレニウス的挙動を示すと推測されていることに関係して,Angell氏(アリゾナ州立大)が低温液体の再配置動力学における分子相関の変化について講演された.近年の大きなテーマである高圧非晶質氷について,その発見者三島 修氏(物材機構)が講演された.不思議なことに高密度と低密度の2種の非晶質氷が存在し,それらは1次相転移で移り変わる.両者の高温側には2種の水が想定され,その先には臨界点があるらしいことも論じられてきた.氏の提唱されるpolyamorphismとあわせ,興味深い研究である.石井菊次郎氏(学習院大)は,水以外にも液体・液体相転移が存在する可能性をpolyliquidismとして提唱された.Tg 直下でアルキルベンゼンを蒸気凝結すると,平衡液体より高い密度のガラスが生成することを見いだすとともに,凝結温度がTg 直下とそれより相当に低温の場合ではガラスの構造が異なり,それから生成する液体の構造も異なることを明らかにされた.自然界の氷は地球環境変化の重要な指標であるが,本堂武夫氏(北大低温科研)は南極大陸に数10万年にわたって堆積した氷の流動性を解析し,流動機構を結晶構造の面から解明したご自身の研究を紹介された.我々のもつ太古の気候像に対して格子不整や点欠陥などの原子分子レベルの研究が本質的な点で寄与したのである.他方,Woodfield氏(ブリガムヤング大)は,粒径の揃った高純度金属酸化物ナノ粒子を固相反応で製造し,構造・磁性・電子物性・熱物性をバルクと比較し,粒度と界面の役割を定量的に追求した研究を紹介された.
一般講演とポスターでは,上述の招待講演に関連した研究に加え,スピン液体・イオン性液体・液晶・細孔中の水分子・有機超伝導体・分子結晶・分子磁性体などの諸物性,熱量計の開発などが報告された.講演していただいた方々は講演順に,山室 修(東大物性研),小林比呂志(工技院計量研),小國正晴,竹内 靖(物材機構),中澤康浩(阪大),阿部 洋(防衛大),Mary Anne White(ダルハウズィー大,カナダ),稲葉 章(阪大),S. L. Ramos(東工大),辰己創一(東大物性研),齋藤一弥(筑波大),譚 志誠(大連化学物理研),阿竹 徹の皆さん.ポスター発表は,浅地哲夫(日大文理),青野祐美(防衛大),渡辺啓介(福岡大),村岡佑樹(阪大),吉元 諒(阪大),上田康平(東工大),名越篤史(東工大),宮崎裕司(阪大),山室(小野田)憲子(東京電機大)の諸兄姉であった.いずれの発表もすばらしい内容で,会場は常に60~80名で埋まり,活発な討論がなされ,充実したセッションであった.発表者には,各地で活躍されている阪大ゆかりの人も多く,関・菅両先生の師である仁田 勇先生の「物質の理解には,構造の側面とエネルギーの側面が車の両輪のようにバランスよく追求されなければならない」という哲学が,脈々と受け継がれていることがわかる.我が国の熱科学の研究は,現在,世界で中心的役割を果している.今後若い世代の人々の活躍で,益々の発展を遂げることを願っている.
セッションの終りに,菅先生が謝辞と研究の想い出を語られた.関先生はご健勝な日々を送っておられるが,記録的な酷暑の中の遠出はお体に差し障りの可能性があるとのことで,残念ながら出席を見送られた.先生はそのことを大変お気になさっておられたが,シンポジウムが盛会で有意義であったことを,心より喜んでおられた.

Emeritus Professor Syûzô SEKI

Emeritus Professor Hiroshi SUGA
 Symposium room
Symposium room
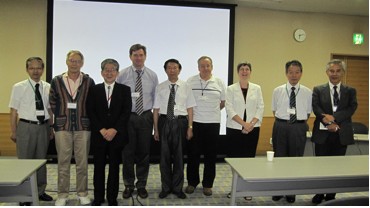 After the session: (Left to right) M. Oguni, C. A. Angell, H. Suga, B. Woodfield,
Z.-C. Tan, M. A. V. Ribeiro da Silva, M. A. White, M. Sorai, T. Matsuo
After the session: (Left to right) M. Oguni, C. A. Angell, H. Suga, B. Woodfield,
Z.-C. Tan, M. A. V. Ribeiro da Silva, M. A. White, M. Sorai, T. Matsuo